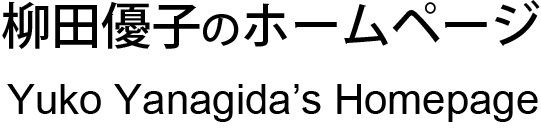上代日本語の「ヲ」について(I)
Vovin (1997)
ここでは、Vovin (1997)の活格説の根拠のひとつである「ヲ」が主語(S)を表示する例を詳しくみていきます。資料調査をするときに注意したい点があります。複文において、主語や目的語が構造的に従属節内にあるのか主節にあるか見極めなければなりません。Vovinの例をよく見るとすべて一見「ヲ」が主語を表示しているように見えますが、実際は主文動詞の内項または目的語です。 (11)Murasakyi no nipopyer-u imwo wo niku-ku araba (MYS 21) Violet Gen be beautiful-Perf-Pt beloved Abs unplelasant-Ger-be Ger ‘If [my] beloved, who is beautiful like a violet, was not beautiful tome.’ (MYS21) (11)の全文は「紫草のにほへる妹を憎くあらば人妻故に我れ恋ひめやも(MYS 21)」です。「妹を」は意味的に「憎くあり」の項であることは確かです。ただ同時に主文の「恋ひ」の目的語でもあります。時代別国語大辞典にも「恋(こふ)」が他動詞として「ヲ」格を取る用例があります。生成文法では、音形のない要素(代名詞はpro、移動の痕跡はtrace)は「適正束縛条件(proper binding condition)」によって先行詞に束縛されなければならないという制約があり、この制約により、(11)のような文であれば、構造的に先行詞であるヲ句は、主文の文頭に、そして従属節の動詞の項には音形のないproが存在します。つまり、[S 目的語ヲ [S pro V] V]](V=動詞、S=文)という構造になります。 (12)Kwosi no kuni sakasi mye wo ari to Kosi Gen province Loc wise woman Abs be-Fin Part kyikasite kupasi mye wo ari to kyikosite hear-Hon-Ger beatiful woman Abs be-Fin Part hear-Hon-Ger ‘[Okuni-nusi] heard that there is a wise woman in the Kosi province, heard that there is a beautiful woman.’ (KK2) Vovinには(12)と同じパターンがもう一例(KK45)ありますがここでは省略します。(Vovinでは(12)の2番目の「麗し女」はゼロ表示(絶対格)になっていますが、実際、万葉仮名「遠」が入っていますので”wo”を入れておきました。)まず(12)はVovin自身も認めているように「ヲ」で表示された要素は「ト」節内の動詞の主語ではありますが、同時に、主文動詞「聞く」の目的語でもあります。現代日本語においては、このような構文を「例外的格付与構文」と言いますが、上代歌謡には多くの例が見られます。「例外的格付与構文」とは、主文の動詞(「思う」など)が従属節内の主語に対格を与える構文です。しかし、Yanagida (2006)では、(12)のような構文は「例外的格付与構文」ではなく、「ヲ」で表示された要素は「ト」節内ではなく、もともと主節動詞の目的語の位置にあるという根拠を示しました。つまり、(12)は、例外的に格付与されたのではなく、「賢し女」「麗し女」は「聞く」の目的語位置にあると解釈されます。「ト」節内の主語には、主節の目的語を先行詞としてとる音声表示のないPROが存在します。(詳しくはYanagida (2006))英語においても例外的格付与構文が歴史的に、PRO構文から「再分析」されたという説があるので、日本語でも同じような歴史的変化が起こった可能性があります。 (13)Imwo wo sita nakyi ni Beloved secretly weep-Inf Cop-Inf ‘My beloved secretly wept (KK78) (13)の全文は「下問ひに我が問ふ妹を下泣きに我が泣く妻を今夜こそは安く肌触れ(KK78)」です。この例では2つの句が並列になっています。「下問ひに問ふ」と「下泣きに泣く」という表現です。時代別国語大辞典ではこの表現はそれぞれ「ひそかに妻どう」「ひそかに泣く」という意味です。つまりVovinが解釈したように、「妹を」が下に続く「下泣きに泣く」の主語ではなく、「下問ひに我が問ふ妹を」と「下泣きに我が泣く妻を」は同格で、共に「安く肌触れ」という動詞句の項です。Yanagida (2006)で示したように、上代語では現代語では「ニ」や「ト」などで表示する動詞句内の名詞句を「ヲ」で表示することが可能です。この例では「愛しい人とやすらかに肌を触れることよ」のような意味だと思います。 (14)Pur-u yukyi wo kosi-ni nadum-yite fall-Pt snow Abs waist-Loc cling-Ger ‘The falling snow clung to [my] waist [and]’ (MYS 4230) 最後に(14)「降る雪を腰になづみて参り来し験もあるか年の初めに(MYS 4230)」について述べます。「なづむ」という動詞は時代別国語大辞典によれば、「とどこおる、妨げられる、難渋する」という意味で、自動詞としての用例が1例あるので、「降る雪」を自動詞の主語として解釈するのが正しいかもしれません。しかし、「降る雪を」は「なづむ」という動詞と「参り来し」という動詞の両方にかかっているように解釈できます。中西進(1983、万葉集四)の現代語訳では「降り積もった雪に腰までうずくまって参上した」とあります。上代日本語では移動動詞の方向や場所など空間を示す名詞の項、たとえば、「難波門を漕ぎでて(MYS 4380)」など、空間名詞を「ヲ」で表示します。現代語でも「海を泳ぐ」「公園を走る」など、移動動詞の項は「ヲ」で表示されます。(14)でも「降る雪」を「参り来し」の項として「降る雪(の中)を参上する」と解釈できるのではないかと思います。 以上、Vovin(1997)のあげた例について考えてみましたが、どの例をとっても、明確に自動詞の主語が「ヲ」で表示されるという強い証拠はありません。 つぎに、「ヲ」に関して竹内史郎(2008)について少し触れたいと思います。竹内の活格説は基本的にVovin (1997)を踏襲しています。「ヲ」を非動作格ととらえ、自動詞の主語が「ヲ」で表示するという例を他にいくつかあげています。しかし、上に述べた理由と同じように「ミ」語法以外は、やはり明確に自動詞主語とは言えない例ばかりです。以下は竹内の例です。 (15) 道の後 古波陀嬢子を 神の如 聞えしかども 相枕まく(KK 45) 竹内によれば、格助詞「ヲ」は「聞え」に対応していて、「聞こゆ」は項をひとつ取る自動詞です。つまり、「古波陀嬢子を」は「聞え」の目的語ではなく主語ということになります。それはそれで正しいと思いますが、(15)の例は、「古波陀嬢子」は主文の動詞「枕まく」の項とも言えます。「枕まく」は「手枕にする」という意味です。構造的には(11)と同様に「古波陀嬢子を」は「聞えしかども」の節内にある主語ではなく、主文の「手枕にする」の対象をあらわす目的語として考えることが可能です。構造的にはこのような文では従属節の主語には音形のないproが存在します。上代語の和歌文では、現代日本語の「ヲ」より広い範囲の内項を表示し、文頭に移動して主題や強調を表す例がたくさんあります。 結論として、上代語の「ヲ」格が自動詞主語(S)と他動詞目的語(O)を表示する絶対格(あるいは非動作格(Inactive))であるという強い証拠は上代語の資料の中からでてきません。「ミ」語法に現れる「ヲ」の問題は残っていますが、この構文をもって、竹内がいうように「ヲ」を非動作格と呼ぶことはできません。小路(1988)によれば、万葉集に「ヲ」は1557例あります。もし「ヲ」が非動作格であれば、主文や従属節を含めてもっとひろい範囲で「ヲ」が自動詞の主語を表示する例があってよいはずです。さらに、もし「ヲ」が非動作格(絶対格)であるなら「ヲ」は歴史的に絶対格から対格へ再分析(reanalysis)されたということになります。私が知るかぎり、言語類型論的に絶対格が対格へ再分析される言語資料は存在しません。その意味でも、上代語の「ヲ」が絶対格であるとは考えられないと思います。 最後に、「ミ」語法に関しては、蔦清行(2005)が興味深い分析をしています。蔦によれば、万葉集では、活用語尾などが、訓仮名で表示される例は稀であるにも関わらず、「ミ」はそのほとんどが「見」という訓仮名で表示されています。そこで、この「ミ」が動詞「見る」に由来し、「ミ思フ」や「ミス」などの言い方は、ミが語尾化することにより意味が失われ、それを補完する形で発達したのではないかと提案しています。蔦の説によれば、ミ語法は、構文的には、例外的格付与構文と同じように、ヲ格名詞は本来「見」の目的語として機能していたことになります。ミ語法の「ヲ」に関しては、蔦の説を支持したい思います。
参考文献 竹内史郎 (2008) 古代日本語の格助詞ヲの標示域とその変化『国語と国文学』50-63. 蔦清行(2005) 「ミの世界」『国語国文』73:12, 10-28
金水・Miyagawa論争
Miyagawa (1989)は古代語の目的語のヲ格とゼロ格についてはじめて生成文法の観点から理論的分析を試みました。Miyagawa はヲ格は形態格、ゼロ格は抽象格として、この二つのタイプの目的語の分布は、統語的に予測可能であると指摘しました。この問題は金水(1993), Miyagawa and Ekida (2003), 金水(2011), Miyagawa (2012)とまだ論争が続いているので「金水・Miyagawa論争」と名付けておきます。Miyagawa(1989)によれば、終止形は抽象格を付与しますが、連体形は名詞的であり抽象格を付与しません。この理論的根拠になっているのが、無助詞目的語は終止形動詞と共起し、連体形動詞とは共起しないという観察です。ヲ格は形態格なので、抽象格を付与しない連体形と共起します。Miyagawaの仮説が正しいかどうかは、「格フィルター」という強い統語的制約がかかる無助詞目的語において、特に、実証的事実の検証が重要になります。しかし、金水(1993, 2011)では、Miyagawa説には多くの例外があり、Miyagawaが主張するような統語的な説明は妥当ではなく、無助詞目的語とヲ格目的語の違いは文体的なものであると主張しました。 本研究では、上代語が活格型であり、平安初期以降の主語表示「ガ」の消失を活格型から対格型への変化と位置づけています。Miyagawa(1989, 2012)も金水(2011)も上代語と平安以降の日本語をとくに区別していませんが、もし格システムが平安初期以降、活格型から対格型へと変化したという説が正しければ、目的語の格に関しても上代と平安を同じ線上で考えるのではなく、別の体系をもつ言語として捉える必要があります。すこしおおげさですが、前にも述べたように言語類型論の観点から、格システムが変化するということは、その言語全体の文法体系に影響することが予想されるからです。 活格説に関連して、Miyagawa (1989)の反例についてひとつだけ指摘しておきます。生成文法理論の観点から、Miyagawa (1989)の反例になりそうな連体形に表れる無助詞目的語のうち、動詞句内にないものは主題である可能性があるので排除しなければなりません。つまり構造的には[S 主題句…[VP pro(あるいは trace) V]]で、目的語は構造的に主題(topic)の位置にあり、VP内には音形のない代名詞pro(あるいは移動の痕跡(trace))が隠されている可能性があるからです。音形のないproには抽象格を付与しなくてよいのかという理論的問題はそれ自体で解決されなければなりませんが、Miyagawa(1989)の例外からとりあえず排除してよいと思います。無助詞目的語が確実にVP内にあると想定される文はその前に音形のある属格主語がある場合です。万葉集の調査では、Miyagawa(1989)の反例になる[主語ガ・ノ 目的語 連体形動詞]の例は55例ありますが(柳田2007参照)この反例には規則性があります。(16)で示すように目的語は名詞単独(N)で現れます。 (16) 松浦県佐用姫の子が (何) 領巾 振りし山の名のみや聞きつつ居らむ (MYS 868) 上代語の散文資料を扱う問題点は「現在の研究」で触れますが、和歌を扱うとき、必ず出てくる問題は和歌の字数制限によるものです。つまり、ここでは、なぜ、「ガ」格の主語が先行すると目的語は単独名詞で表れるのか、という問題に対して、まず考えられる答えは和歌の字数制限です。しかし、字数制限が問題であれば、なぜ字数を整えるために2語以上の句や「ヲ」格表示された目的語がこの位置に来ないのでしょうか。和歌の字数制限の問題では単独Nの規則性を説明できません。また、たとえ和歌とは言え、字数制限を整えるため、文法を逸脱した、いわゆる「非文 ungrammatical sentence)を私たちは使うでしょうか。これは実際、現代の和歌でも調べてみることはできるかもしれませんが、ここでは和歌であっても、その言語の基本文法に従っていることを前提としたいと思います。話をもとにもどすと、Yanagida (2007)で、(16)のような例文において、動詞に隣接した名詞が単独のNで表れるという規則性は、Nが統語的に名詞編入(Noun Incorporation)されているのではないかという仮説を提案しました。Baker (1988)によれば、編入された名詞は格付与を受けないので、(16)はMiyagawa (1989)の反例にはなりません (Yanagida 2007) 。実際、能格・活格言語にこうした不定名詞が編入される、いわゆる「派生自動詞」をもつ言語が多いことが知られています。歴史的にいつ頃までこのような名詞編入する自動詞構文が存在していたのかは平安時代以降の資料を調査しなければわかりませんが、Miyagawa (2012:271)の調査によれば、少なくても平安以降も名詞編入操作が存在していたのではないかと考えられます。 最後に、本研究のこれまでの分析は上代の和歌文の詳細な調査によります。上代散文資料に関しては、Frellesvig and Wrona (2009)が、Miyagawa (1989)の検証として、宣命、祝詞におけるヲ格目的語と無助詞目的語の分布について詳しく調査しています。彼らの結論はヲ格とゼロ格は文体的違いであり、無助詞目的語を単に随意的なcase dropであると分析しています。しかし、上代の散文資料である宣命体から助詞を扱うときには大きな問題点があり、これにかんしては、以下で。 参考文献 Baker, Mark.C. (1988) Incorporation. Chicago: The University of Chicago Press. Frellesvig, Bjarke and Janick Wrona (2009) The Old Japanese case system: The function of wo. Japanese/Korean Linguistics 17, 565-79. Stanford: CSLI Publications. ・金水敏(1993) 「古典語の「ヲ」について」『日本語の格をめぐって』仁田義雄篇、pp.191-224.くろしお出版 ・金水敏(2011)「統語論」『文法史』金水敏、高山善行、衣畑智秀、岡崎友子篇、3章 77-166頁 岩波書店 ・Miyagawa, Shigeru (1989) Syntax and Semantics: Structure and Case Marking in Japanese 22. New York:Academic Press. ・Miyagawa, Shigeru and Fusae Ekida (2003) Historical Development of the Accusative Case Marking in Japanese as Seen in Classical Literary Texts. Journal of Japanese Linguistics 19, pp 1-95. ・Miyagawa, Shigeru (2012) Case, Argument Structure, and Word Order, Routledge leading Linguists. ・Yanagida, Yuko (2007) Miyagawa’s (1989) Exceptions: An Ergative Analysis. MITWPL.
続日本紀宣命の「ヲ」について
上代日本語では目的語は、「ヲ」格表示かゼロ格で表記されますが、続日本紀宣命の、ヲ格表示とゼロ格表示の分布を調査する上で、大きな壁があります。万葉集など上代和歌では、返読文をのぞけば、ほとんどの用例で万葉仮名の「ヲ」で表示されていない目的語は、無助詞目的語と解釈してよいと思いますが、宣命では、助詞が万葉仮名で表記されていない場合、「ヲ」を読み添える場合があります。池田(1996)の調査では、本居宣長『続紀歴朝詔詞解』では83例の読添え、北川和秀の『続日本紀宣命 校本・総索引』では85例の読添えがあると述べています。また池田氏自身の調査では読添え例は125例とさらに多くなっています。読添えの基準に関して池田氏は以下のように述べています。「「ヲ」格の表記されている目的語と動詞の組み合わせを抜き出し、それらをもとに同じ目的語と動詞の組み合わせで「ヲ」格無表記の例を抜き出すという方法をとる(1996:20)」。しかし、池田氏の調査では、目的語と動詞の組み合わせに動詞の活用を考慮に入れていません。つまり、動詞が連体形でも終止形でも同じ目的語と動詞の組み合わせならばいずれも「ヲ」の読添えがあるものとして調査しました。この採取基準は問題があると言わざるをえません。さらに北川氏の『続日本紀宣命 校本・総索引』には、どのような基準で読み添えを行ったかに関する言及はなく、おそらく本居宣長『続紀歴朝詔詞解』に従ったものと思われます。いずれにしても、宣命の「ヲ」の読添えに関しては、ほとんどわかっていないのが現状であると思われます。上代散文資料のヲ格、ゼロ格の分布を調査する上で、読添えに関する問題を無視できません。 参考文献 青木和夫,他(1989-1992)『続日本紀(1?3)新日本古典文学大系』岩波書店・池田幸恵(1996)「宣命の「を」格表示」待兼山論叢 30号19-32.大阪大学文学部・金子武雄(1941)『続日本紀宣命講』東京図書出版・北川和秀(1982)『続日本紀宣命 校本・総索引』吉川弘文館・小谷博泰(1986)『木簡と宣命の国語学的研究』和泉書院 大阪・松尾拾「平安初期に於ける格助詞「を」」国語と国文学15-10