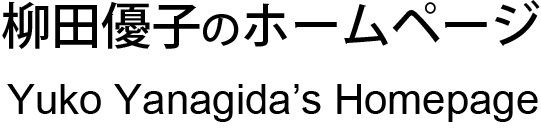3つの類型的格システム
(1) a. 太郎が本を買った.
b. 太郎が帰ってきた.
(2)の能格型言語は、Dixon(1994)の研究で有名なジリバル語など、自動詞の主語と他動詞の目的語が同じ絶対格表示(絶対格の多くは無表示です)をとり、他動詞の主語は能格として異なる表示がされます Dyribal (Dixon 1994:161)。
(2) a. ŋuma yabu-ŋgu bura-n.
father.ABS mother-ERG see-NONFUT
‘Mother saw father.’
b.yabu banaga-nyu.
mother.ABS return-NONFUT
‘Mother returned.’
(3)の活格型言語はグアラニ語など、自動詞が、動作動詞と非動作動詞の主語で格の分裂(split)が起こり、動作自動詞の主語は他動詞の主語と同じ活格表示、非動作自動詞の主語は他動詞の目的語と同じ絶対格表示をとります Guaraní (Mithun 1991)。
(3) a. a-xá. ‘I go.’
b. a-puá. ‘I got up.’
c. a-gwerú aína. ‘I am bringing them now.’
d. še-rasí. ‘I am sick.’
e. še-ropehií. ‘I am sleepy.’
活格は能格の一形態であるという考え方があり、1)の「対格型システム」に対して、2)と3)を「非対格型システム」と呼ぶことがあります。 いずれにしても、言語はこの3つの格システムのどれかに属し、格システムはその言語の格だけでなく、語順や代名詞体系など言語全体の文法的特徴を反映するため、言語の骨格のようなもので、格システムが変化すると、その言語全体の類型が変わると考えられています。Harris and Campbell (1995)は、こうした格の類型を、英語でAlignmentと呼び、現在までこの用語が使われています。
活格型言語は、格システムにおいて、自動詞が動作動詞と非動作動詞に分裂(split)するのですが、自動詞がどのように分類されるかは言語によってかなり異なります。グアラニ語なども実際は動作がないように見える状態動詞などに活格が表れたりします。 また、能格・活格型言語は動詞の種類だけではなく、主語がSilverstein (1976)の名詞階層のどの位置にあるかで分裂が起こることが観察されています。名詞階層で分裂が起こる場合、能格は無生物など、名詞階層の低い名詞に現れ、代名詞などの名詞階層の高い名詞は絶対格(あるいは主格)が現れるという一般化があります。一方、活格は代名詞などの名詞階層の高い名詞に現れ、無生物主語など名詞階層の低い名詞句は絶対格(あるいは主格)で表示されます。 このように、非対格型言語は、さまざまな言語環境で分裂格システムをもつことが知られています。たとえば、ヒンズー語は能格言語であると言われることもありますが、正確には活格言語です。-ne は動作自動詞(非能格自動詞)と他動詞の主語をマークし、非動作自動詞(非対格自動詞)はゼロ表示です。(4-5)はMohanan (1994)からの例です。(4a-b)で示すようにヒンズー語は過去や完了形動詞は活格型、非過去は主格・対格型で表れる分裂活格言語です。しかし、 (5)で示すように形態的対格は活格型のパターンにも表れます。Mohananによれば、ヒンズー語では形態的対格は有生名詞に現れ、無生名詞の場合は定名詞に現れます。
(4) a. Ravii-ne kelaa khaayaa.
Ravi-ERG banana-ABS eat-PERF
‘Ravi ate the banana.’
b. Ravii kelaa khaa rahaa thaa.
Ravii-NOM banana-ACC eat PROG be-PA
‘Ravi was eating the banana.’
(5) a. Ilaa-ne ek bacce-ko uthaayaa.
Ila-ERG one child-ACC lift/carry-PERF
‘Ila lifted a child.’
b. Ilaa-ne haar-ko uthaayaa.
Ila-ERG necklace-ACC lift-PERF
‘Illa lifted the/*a necklace.’
非対格(能格、活格)システムは文字どおり対格がないと考えがちですが、実際は、ヒンズー語やジリバル語など、多くの非対格型言語は形態的対格をもっています。ジリバル語は代名詞と普通名詞で格の分裂が起こります。普通名詞は能格型で、代名詞は対格型で表示されます。しかし、主語が普通名詞、目的語が代名詞の場合は、(6)で示すように、主語に能格、目的語に対格が表れます。
(6) ŋana-na jaja-ŋgu ŋamba-n.
we-ACC child-ERG hear-NONFUT
‘The child heard us.’
ジリバル語はSOV言語ですが、能格型はOSV語順で現れます。その意味では、(6)は統語的には能格型と言えます。Alignment の観点からこうした分裂格システムをどう説明するか、さらに、歴史的にAlignmentの変化がどのような言語的トリガーによって引き起こされるか、また非対格型システムの再建(reconstruction)の問題など、今日まで生成文法理論、言語類型論を問わず大きな議論になっているわけです。 また、言語類型的にはこうした言語の格システム(alignment)は歴史的に変化することが観察されます。
参考文献 Bittner, Maria and Ken Hale (1996) The Structural Determination of Case and Agreement.Linguistic Inquiry 27.1-68 Dixon, R.M.W. 1994. Ergativity. Cambridge: Cambridge University Press Harris, Alice C. & Lyle Campbell. 1995. Historical Syntax in Cross-Linguistic Perspective.Cambridge: Cambridge University Press. Mithun, Marianne. 1991. Active/agentive Case Marking and its Motivations. Language,67.3: 510-546. Mohanan, Tara 1994. Argument Structure in Hindi. CSLI publications. Stanford University. Silverstein, Michael. 1976. Hierarchy of Features and Ergativity. In Grammatical categories in Australian Languages, ed. R.M.W. Dixon, 112-171. Canberra: Australian Institute of Aborignal Studies.
上代日本語の活格性
(8)主語目的語
動作動詞 iwo/Ø
非動作動詞wo/Ø
(9)はVovinが主張する活格「イ」の例、(10)は「ヲ」とゼロ格が非動作動詞の主語を表示する例です。すべてVovin (1997)からの引用例です。
(9) papa i mor-edomo…
mother Act guard-Ger
‘Though [my] mother guards [me]…’ (MYS XIV-3393)
(10) a. miyako wo topo-myi
capital Abs far-Ger
‘because the capital is far…’ (MYS I-51)
b. …kuni Ø topo-myi ka mo
province Abs far-Ger Part Part
‘Is it because the province is far?’ (MYS I-44)
その後、Vovin (2010)では「イ」が宣命などに用例が偏っていることなどを根拠に「イ」は朝鮮語からの借用語であり、Vovin (1997)の活格説を取り下げました。さらに、上代資料では、「ヲ」が非動作動詞の主語を表示する例がありますが、その例は非常に限られた構文だけです。よく知られた構文としては(10)にあるような、いわゆる「ミ語法」の主語はゼロ格か「ヲ」で表示されます。しかし、「ヲ」が絶対格であれば、非常に多くの用例がある連体節内の非動作自動詞の主語を「ヲ」で表示してもよさそうですが、そうした例は見当たりません。そもそもVovin(1997)が「ヲ」が対格ではなく、絶対格であるという提案をした背景には活格型言語では目的語を絶対格で表示するという前提に立っているためです。しかし、上のヒンズー語の例で見たように、類型的には多くの能格や活格型言語は形態的対格を持っているという事実から、上代語でも「ヲ」は対格表示として機能していると考えるのが自然です。しかし、最近、Vovin (1997)に従い、日本の国語学者の中からも上代語の「ヲ」を根拠に日本語の活格性を主張する論文もでてきているので、Vovin(1997)の活格説の根拠になっていた「ヲ」が主語を表示する例をあとで詳しく見て行きます。 Vovin (2010)と同様に、Whitman and Yanagida (2011)では上代散文資料また平安初期の訓点資料に見られる「イ」は朝鮮語からの借用であり、主格型を示すことを述べました。ここでは、本研究で2005年以来提案してきた、上代日本語の「ガ」が活格を表示するという根拠について簡単にまとめたいと思います。まず第一に、上で述べた非対格型言語の格配列に共通するSilverstein(1976)の「名詞階層」に「ガ」が従っていることです。名詞階層のもっとも高い1・2人称の弱形代名詞(deficient pronoun)は「ガ」が必須であり、名詞階層の低い無生物普通名詞は一般に「ガ」で表示されません。第二に、「ガ」は「行く」など動作動詞に現れますが、「咲く」などの非動作動詞には現れません。上にあげたヒンズー語と形態的には似ています。現代日本語が名詞や動詞の種類に関係なく主語が「ガ」で表示されるのとは対照的です。上代日本語の「ガ」とゼロ格の分布は以下のような活格型を示します。
(7) 主語目的語
動作動詞 ga Ø
非動作動詞Ø
3つめの根拠は、多くの活格言語が、属格と活格が同形(case syncretism)を示すことです。上代語の「ガ」を扱う先行文献で「ガ」が主語を表示するときに、現代語の延長線上で「主格」と捉えているものが多くあります。しかし、理論的観点からも類型論の観点からも、上代語における「ガ」で表示された主語は、属格主語(genitive subject)と呼ぶべきです。実際、終止形などの主文の主語を「ガ」で表示できないのは、「ガ」が属格であるからです。現代語の属格「ノ」が関係詞内の主語を表示できても、主文主語を表示できないのと同じ理由です。属格主語については後で詳しくみていきたいと思います。最後に、4つめの根拠は、統語的特徴です。主格主語は統語的に主語の位置(生成文法的にはTPの指定句)へ移動します。しかし、上代語の「ガ」は主語の外項主語位置(生成文法的にはvPの指定句)からの移動が起こりません (柳田(2007),Yanagida and Whitman 2009参照)。主語が外項主語位置に基底生成されTPの位置へ移動しないという統語的制限は、能格・活格言語に多くみられ非常に普遍性が高い事実です(Bitter and Hale (1996)など多数参照)。
参考文献 Vovin, Alexander. 1997. On the Syntactic Typology of Old Japanese. Journal of East Asian Linguistics 6: 273-290. Vovin, Alexander. 2010. Koreo-Japonica: A Re-Evaluation of a Common Genetic Origin.Hawai’i Studies on Korea. Honolulu: University of Hawaii Press and Center for Korean Studies, University of Hawaii.